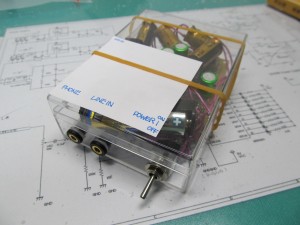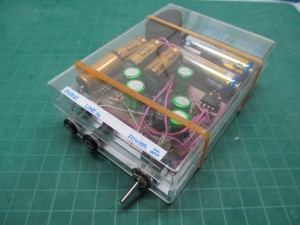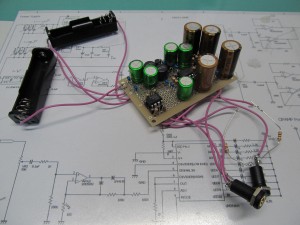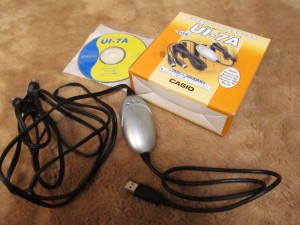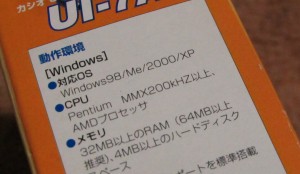予算がなかなかまわらんので普段はPCのセキュリティはフリーのものですませてしまう。
現在使用しているのはAvast!バージョン8。ところがふとタスクトレイのアイコンを見ると停止している。
ウィンドウを開くと「登録されていません」などと表示されていた。どういうことだろうか。
登録してくださいもなにも、先月更新したので期限が切れているはずもなく、再インストールしてみたが一向に改善しない。
ググってみると、どうやらMacTypeと相性が悪いらしく、MacType側から「除外」してやらなければならないらしい。
なるほど。
その後MacTypeのプロセスマネージャからAvast!を除外してやると、正常に動作するようになった。